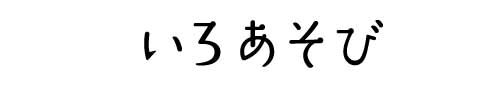年が明けて7日は「七草がゆ」を食べる行事。
「一年、何事もなく過ごせますように」と
無病息災を願い、春の七草を入れた
七草がゆをいただきます。
七草には「春の七草」と「秋の七草」があり、
春の七草は、
芹(セリ)、薺(ナズナ ※ぺんぺん草)、
御形(ゴギョウ)、繁縷(ハコベ)、
仏の座(ホトケノザ)、菘(スズナ ※かぶ)、
蘿蔔(スズシロ ※大根)。

昔から食用として知られています。
セリ科セリ属の多年草。
水田や水辺、湿地帯で多く育ち
独特の良い香りがします。
薺(ナズナ)
別名はペンペン草。
アブラナ科スズナ属の越年草。
道端や田畑で良く見かけられ、
花の時期には白い花が咲き、
平たい三角形の実がつきます。
三味線のバチに似ているので
ぺんぺん草とも言われています。
御形(ゴギョウ)
別名は母子草(ハハコグザ)。
キク科ハハコグザ属の越年草。
全体が白い綿毛に覆われ白っぽく、
花の時期には黄色い花がきます。
繁縷(ハコベ)
ナデシコ科ハコベ属の越年草。
田畑や道端でみかけられ時期には
白い小さな花が咲きます。
仏の座(ホトケノザ)
別名はコオニタビラコ。
キク科ヤブタビラコ属の越年草。
水田や河川敷などで見られ黄色い
小さな花がさきます。
また、秋の七草は
萩(ハギ)、尾花(オバナ ※ススキ)、
葛(クズ)、撫子(ナデシコ)、
藤袴(フジバカマ)、女郎花(オミナエシ)、
桔梗(キキョウ)。
秋の9月下旬、十五夜には月の見える窓辺に
月見団子と花瓶、秋の七草のススとを
お供えする風習があります。